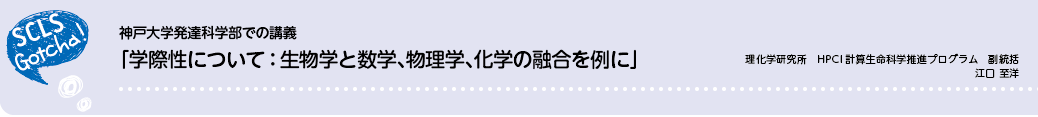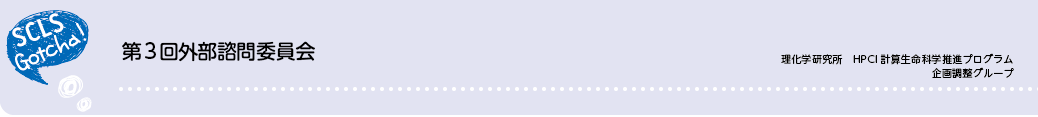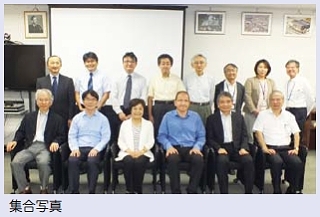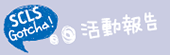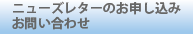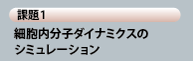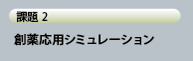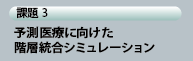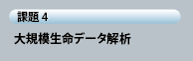2015年6月19日と26日に「学際性について」と題した講義を行いました。この講義は神戸大学発達科学部が新入生に対して行う「発達科学への招待」の1コマとして行われているもので、キーワードは学際性です。私は過去4年にわたって講義する機会を与えられてきました。昨年までは『21世紀に入り、「京」を中心とするスーパーコンピュータと、DNAシークエンサーなどの計測技術の急速な進歩が、生物学と数学、物理学、化学の融合を促進してきている』ことを主なテーマとし、学際性について話してきました。今年度も大筋に変化はありませんが、昨年度、発達科学部の中でも文系に所属する学生から「私は文系ですが、社会に出ていくと理系が有利と言われます。どうでしょうか。」という質問を頂いたこともあり、文系と理系の調和ある発展が社会にとって必要であるし、実社会で出会う問題の解決には文理融合した知識が求められる点も強調することにしました。実際、ゲノム編集技術による「デサインされた赤ちゃんDesigner Baby」の創出が今、世界的な問題になってきています。理系の研究者は「自分の行っている研究は善である」という考えを持っており、そうでないと創造的で先進的な研究を行うことはできません。そう考えることは自然で通常は正しいのですが、その研究を今進めるべきか、あるいはその研究成果を社会が受容するかどうかは別問題で、文系と理系の両分野の知識を十全に踏まえた考察が求められます。学生が「学際性」を考えるにあたって、学問領域の広がりと探究する深さという2つの軸で考えてはどうだろうかと提案しています。例えばT字型人間やΠ字型人間です。計算生命科学は計算科学と生命科学の2つの足を持ったΠ字型人間が取り組む学問領域と言えます。当然その2つの足を結ぶ線上には生命倫理などの文系知識が必須です。学生からは「くさび型人間がいい」という予想外の意見も寄せられました。若い人が創造的に新しい学際的研究領域を作り上げていってくれることを切に願っています。